音
ストローでピー! 音しらべ実験


 材料
材料

- ストロー (3~4本 ※プラスチックのもの)
- はさみ (1本)
- 定規 (1本)
 実験の手順
実験の手順
STEP 1
<実験1>ストローを10cmほどの長さに切る
(曲がるタイプのストローは、あらかじめ曲がる部分を切り落としておく)
(曲がるタイプのストローは、あらかじめ曲がる部分を切り落としておく)
STEP 2
ストローの先端を3cmほど指で押しつぶして平らにする
STEP 3
ストローの平らにした方をはさみで斜めに切り、山型にしておく。
※細かな作業なので、小さなお子さんはお家の方に切ってもらおう!
※細かな作業なので、小さなお子さんはお家の方に切ってもらおう!
STEP 4
山型に切った方を口につけ、息を強く吹き込んでみる
「ストローは、どうなった?」
※ストローの先端で舌を傷つけないように注意しよう。
「ストローは、どうなった?」
※ストローの先端で舌を傷つけないように注意しよう。
STEP 5
<実験2>新しいストローを15cmほどの長さに切って、②から④まで同じように実験する。
「ストローから出る音に変化はあったかな?」
「またそれはどんな変化だったかな?」
「ストローから出る音に変化はあったかな?」
「またそれはどんな変化だったかな?」
STEP 6
<実験3>新しいストローを使って、自分で長さを決めて②から④まで同じように実験する。
「10cmよりも短くしたら、音に変化はあるかな?」
「15cmよりも長くしてみたら、音に変化はあるかな?」
10cmを基準にして長さを工夫してみよう!
「10cmよりも短くしたら、音に変化はあるかな?」
「15cmよりも長くしてみたら、音に変化はあるかな?」
10cmを基準にして長さを工夫してみよう!


 解説「どうして、こうなったの?」
解説「どうして、こうなったの?」
「音」とは、ものの震えが耳まで伝わるものです。普段は、空気を伝って耳まで届きます。今回は、ストローの中に息を吹き込むことでストローの中の空気を振動させていました。
音の高さの違いは、その音の振動数が関係しています。同じ時間の中で、振動した数が多ければ高い音、少なければ低い音になります。この振動数のことを周波数とも言います。今回の実験では、ストローの長さを調整することでその音の違いを感じた、というわけです。
また、10cmを基準にすることで科学の基礎的な力である「比べる」という要素も入っています。紙に長さや音の特徴などを記録すると、立派な自由研究になりますね。
 さらにすすんで
さらにすすんで
- ストローの太さを変えてみたら、音に違いはあるかな? 色々なストローで試してみよう。
- ストローの長さを調整してドレミのような音階は作れるかな?


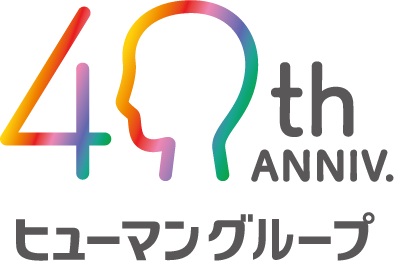
 教室検索
教室検索




