動物
セミのぬけがら観察隊!


 材料
材料
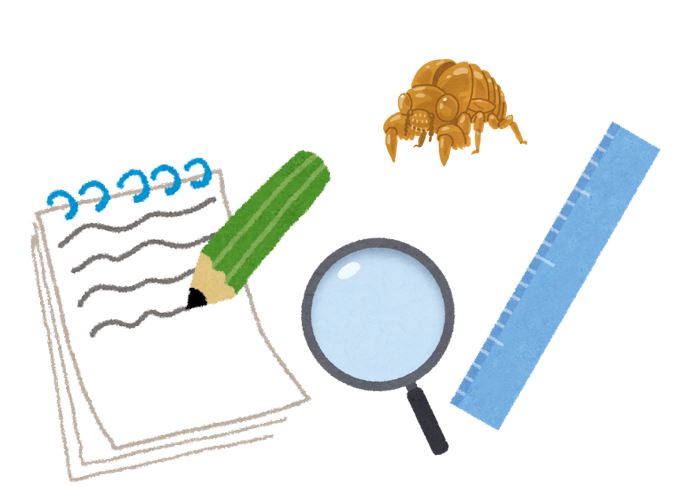
- セミのぬけがら
(1つ 衛生面を考え、できるだけ木についているもの) - 定規 (1本)
- 紙と鉛筆 (1つずつ 記録用に用意しておく)
- 虫眼鏡やルーペ
(細かいところまで観察できるがなくてもOK)
 実験の手順
実験の手順
STEP 1
大きさを測ろう
頭から腹の先までの長さで、セミの種類が分かる
→26ミリメートルよりも大きいものは、アブラゼミ、ミンミンゼミ、クマゼミの可能性が高い。
→26ミリメートルよりも小さいものは、ニイニイゼミ、ヒグラシ、ツクツクボウシの可能性が高い。
頭から腹の先までの長さで、セミの種類が分かる
→26ミリメートルよりも大きいものは、アブラゼミ、ミンミンゼミ、クマゼミの可能性が高い。
→26ミリメートルよりも小さいものは、ニイニイゼミ、ヒグラシ、ツクツクボウシの可能性が高い。
STEP 2
裏返してオスかメスかを見分けよう
ぬけがらを裏返しにして、腹の先を見てみる
→腹の先にタテの線が入っていたら、それはメスのセミ。
メスは幼虫のときから産卵管(さんらんかん)をもっているので、
このような特徴的な線がはいっている。
ぬけがらを裏返しにして、腹の先を見てみる
→腹の先にタテの線が入っていたら、それはメスのセミ。
メスは幼虫のときから産卵管(さんらんかん)をもっているので、
このような特徴的な線がはいっている。
STEP 3
セミが呼吸をしている穴を見つけよう
腹の側面に、セミが呼吸するときに使っている穴がいくつか開いている。
見つけてみよう。
腹の側面に、セミが呼吸するときに使っている穴がいくつか開いている。
見つけてみよう。
まとめ
調べて分かったことを、紙に記録しておこう。
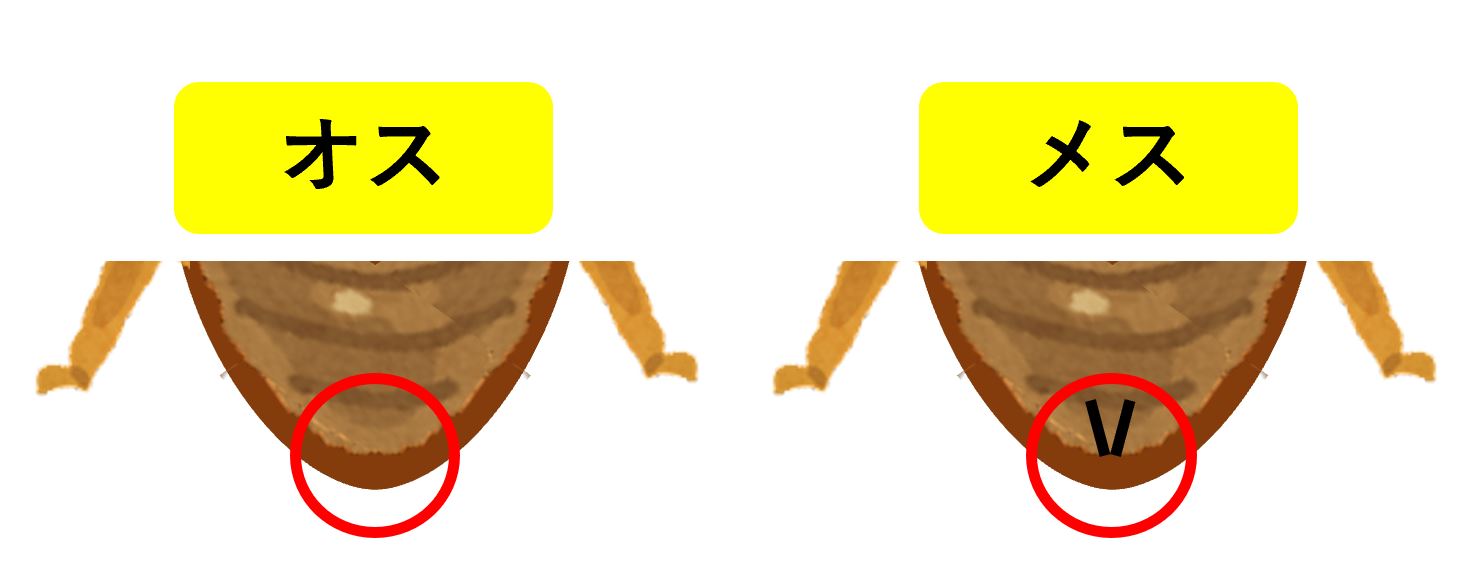
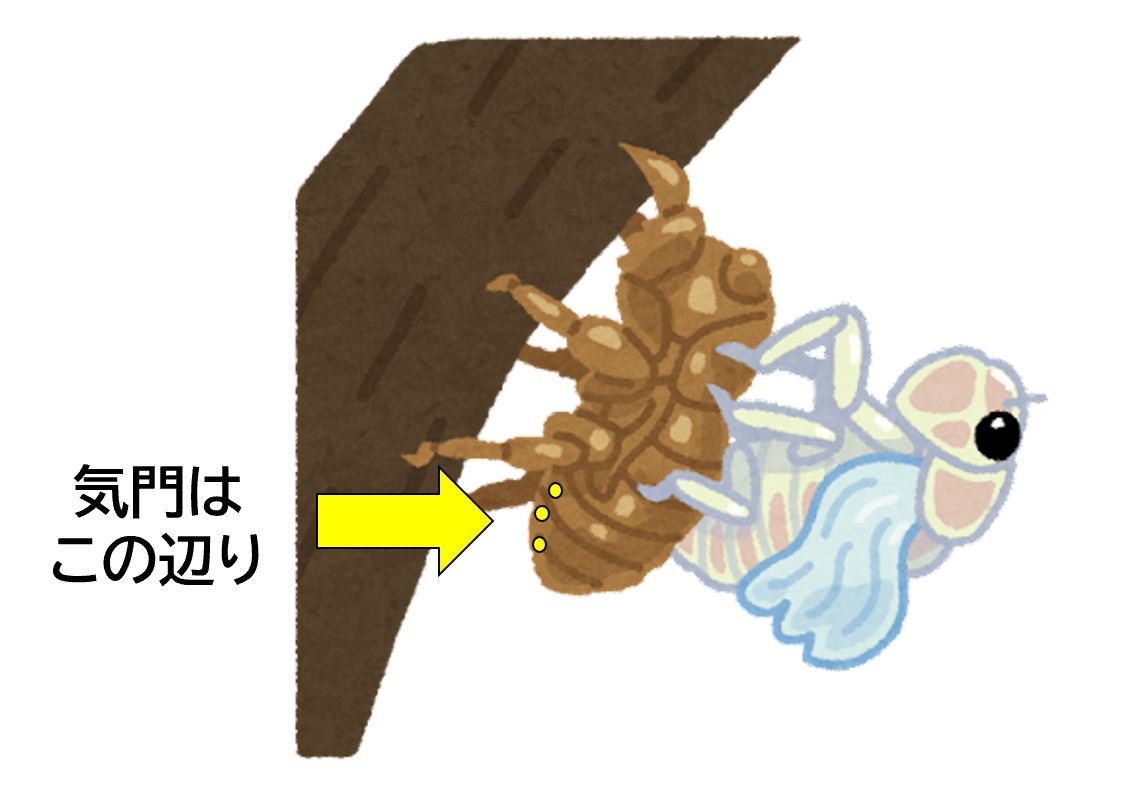
 解説「どうして、こうなったの?」
解説「どうして、こうなったの?」
ここでは<ステップ3>のセミの呼吸について解説します。 人間や魚、動物は、肺やえらや皮膚を使って呼吸をしています。セミのような昆虫は、少し変わっていて「気門(きもん)」と呼ばれる小さな穴を使って呼吸をします。ちょうど、腹の側面のあたりです。セミのぬけがらを見ると、その穴がくっきり見ることができます。ぬけがらにも、生き物の生態のヒントが隠されているのですね。
▶大人の方へ
この実験で一番大切なことは、お家の人が虫を「気持ち悪い」と言わないことです。お子さまは、大人が思っている以上にご家族の言葉に影響をうけます。お子さまたちの「好き」を削ぎ落さないためのお願いです。虫が苦手な方は「苦手だけど、それは初めて知ったよ」「触れないけど、ユニークで面白いね」程度に留めておいていただけると、お子さまたちの可能性を広げることができます。
 さらにすすんで
さらにすすんで
◆他の生き物も見てみよう
気門は、カブトムシやクワガタなど大きい昆虫だと、よりはっきり見ることができます。


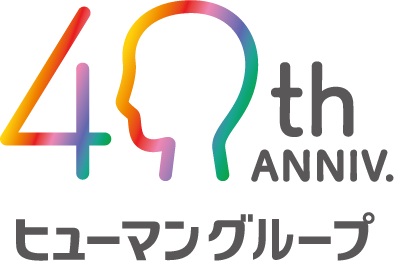
 教室検索
教室検索




