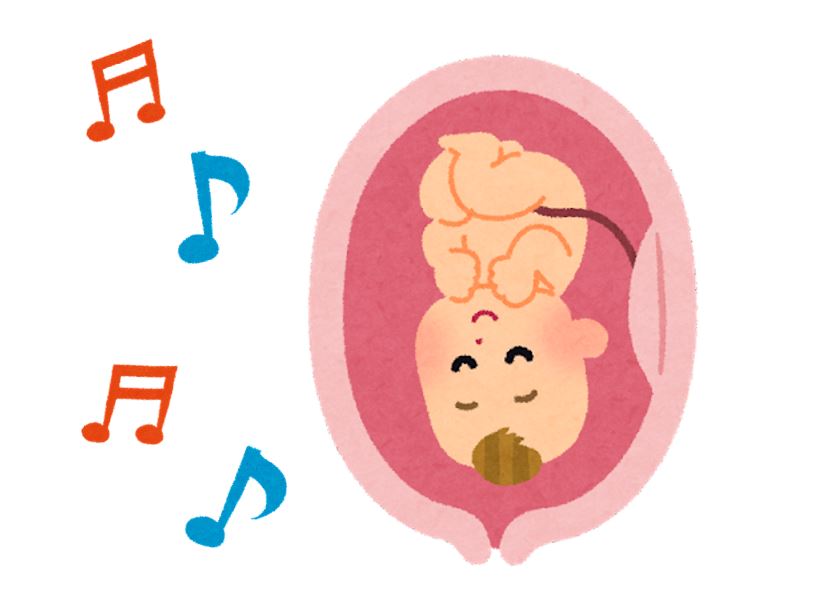かたつむりのようにゆっくりと~聴覚の仕組み~

雪が降ると、音が雪に吸収され静かになり、より一層寒さを感じそうです。
ということで、今回のテーマは「音」です!
かたつむりのようにゆっくりと~聴覚の仕組み~
- 産まれる前
- 産まれた瞬間
- 生後2・3か月
私は「サイエンス」のせかいのプリンセス「リカ」よ。
クイズの答えはわかったかしら?
正解は、
1.産まれる前
でした!
ここからは、先生に教えてもらいましょう。
人間はいつから音が聞こえる?
子育て経験のある方は、ご存じだったかもしれません。
赤ちゃんはお腹にいるときからすでに外の音を聞いています。
もう少し詳しくみていくと、妊娠4~5週頃から耳の溝や隆起ができはじめ、妊娠3か月頃には耳の外側の形が出来上がります。
妊娠7か月頃には、耳の中の様子も大人と変わらないくらいに成長します。
そんなに早く耳ができるのね!
耳の形成や成長にともない、妊娠20週(6か月頃)には、お母さんの血流や心臓の音が聞こえるようになります。
そして、妊娠28~30週(8か月頃)には外の音や声が聞こえるようになると言われています。
特に高い音が良く聞こえるようで、お母さんの声に反応するそうですよ。
お母さんの声が低い場合には…どうなっちゃうのかしら…笑
こうして産まれてから成長にともない、少しずつ音を正確に脳に伝える神経ができあがってきます。
生後2~3か月頃には、周りの音や人の声に目を向けるようになります。
なるほど…
ちなみに、人間の感覚の中で最後まで機能しているのは「聴覚」と言われています。
ケガや病気などで寝たきりになった場合や、意識レベルが低下した場合でも、周りの音は聞こえていると言いますね。
これは聴覚が他の運動機能をともなわずに役割を果たせるからです。
耳の機能が保たれ脳に血流がいっていれば、まぶたを開けたり筋肉を動かしたりしなくても、周りの音は聞こえているのです。
聴覚ってすごいのね!
音が聞こえる体の仕組み
では、今度は「音が聞こえる体の仕組み」を見ていきましょう!
音は、耳やその内部器官をふくめ主に外耳・中耳・内耳という3つの部分を伝わっていきます。
音は空気の振動として耳に伝わります。
その振動は、耳介(じかい)と呼ばれる部分に集められ、外耳道(がいじどう)を通ります。
この耳介と外耳道の部分を「外耳」と呼びます。
その後、振動は鼓膜に伝わります。
「中耳」の鼓膜が振動すると、その振えは耳小骨(じしょうこつ)という3つの小さな骨で増幅されます。
よく子どもがなる耳の病気「中耳炎」は、細菌やウイルスの感染でこの中耳部分に炎症が起こることをいいます。
そして、その奥の「内耳」の一部である蝸牛(かぎゅう)が、振動として伝えられた音を今度は電気信号にかえます。
この電気信号が神経を通して脳に伝わることで、私たちの耳から入った音は脳に伝えられるわけです。
振動を電気信号に換える仕組みを私たちの身体が持っている…なんだか不思議な話だわ!
ちなみに、この蝸牛はカタツムリの形に似ていることから、その名前が付けられているんですよ。
確かにカタツムリの渦巻きのようね!
人間に「聞こえる」という仕組みが備わっていることは生きていく上でとても重要ではありますが、
一方で、音が聞こえなくてもコミュニケーションをとったり危険を回避したりする方法もあります。
手話、ユニバーサルデザイン、動物にいたってはエコーロケーションというものもありますね。
私たちの身体が音を電気信号に変えるように、音が聞こえなくてもそれを様々な形に変える努力を人は積み重ねてきました。
かたつむりのようにゆっくりな足取りでも、私たちは確実に進化しているのです。
「今」を前向きに変えようとしている人々の努力や歩みは、止まることはありません。


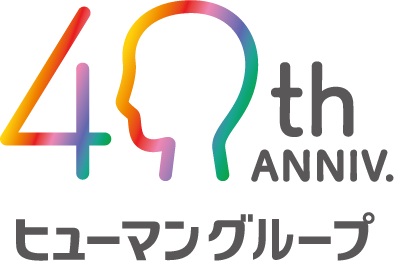
 教室検索
教室検索